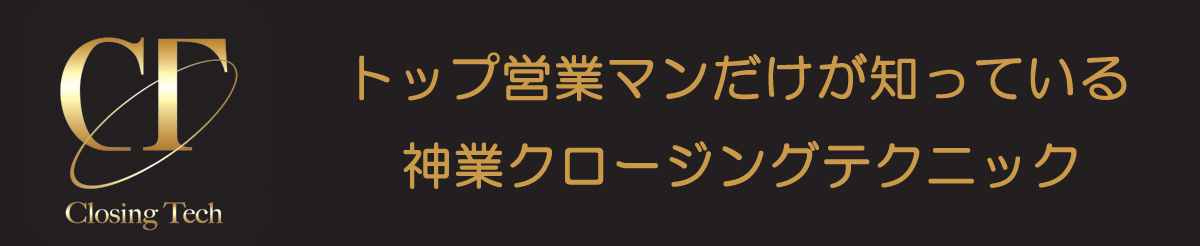営業マンのバックグラウンドとプロスペクトの心理
<優秀なのに首になりかけた営業マン、ウェブの話>
私が親交のあったウェブは、ヴァージニア・ビーチにある中産階級のエリアで家具の販売をする有能なセールスマンでした。ある日、ウェブの上司でもある私の友人のポールを訪問しました。
彼は造船所の労働者のなどのブルーカラーの人たちや市役所の職員など、年収6000ドルから10000ドルの客層を相手に販売活動する店舗と粒ぞろいの従業員を抱えて、商売をしていました。
ポールが彼の部下を私に紹介してくれたとき、彼の非の打ちどころがない身だしなみと正確にソフトに調整された声のトーンに驚かされました。ベストを着用し、お堅い感じの眼鏡、目立たないスーツと完璧に調和したネクタイをしていました。典型的な大学の教授タイプの身なりでした。
いっしょにランチを取っていた時に、それまでウェブのことは頭になかったのですが、ポールが彼をもうすぐ解雇するという話をし始めました。 ウェブは最高レベルの営業成績が残せてもおかしくない人材なので、彼を切ること自体、恐ろしいことだと言うのです。
「君の話を聞く限り、彼はアルコール中毒でもなさそうだし、他に大きな欠点もなさそうだ。彼のどこが悪いの。それとも、君とか私程度の人間といっしょに働くには、自分が優秀すぎるとでも思っているのかい。」
「君がいみじくも言ったことには興味をそそられるね。ウェブはいい奴だし俺たちとは別格だとも思っていない。ただ、商談の最終局面に差し掛かるまでは申し分ないのだが、結局決めることができず、失注してしまうのさ。何度も何度も。」
「俺が興味をそそられたのは、『自分が優秀すぎると思っているのか』と君が聞いたことだよ。セールスマンとしては、品が良すぎるという意味で言ったんだよね?」
「自分がどういう意味でそう言ったのかよくわからないが、彼のしゃべり口調は大学教授風で他人行儀で控えめ、平均以上の教育や経歴をもっている品格の人であることは確かだよ。なあ、ポール、どうして彼は家具を売っているんだ?」
「好きだからだと言っていたよ。どう見ても営業が好きそうだし。夜早めに家に帰ることもない。全力で販売しているよ。熱意もある。働き過ぎくらいだ。」
我々二人はショールームに戻りました。その途中、なぜ彼が客の決定ボタンという心のボタンを押せないでいるのかを見つけ出して、彼のたすけになろうと心に決めました。(彼がそれを拒まなければの話でしたが…)
私は、彼との会話を開始しました。彼と10分間会話を交わし、他の営業マンたちの彼への冷やかしを聞いたところで、私は答えにたどり着いたと思いました。彼はプロスペクトたちとIdentify(同化する、同一視する)できてなかったのです。同じ目線上にいなかったのです。
彼は、平均的な家庭、つまり高校教育か専門学校くらいまでの教育を受けた労働者の人々にたいして平均的な価格の家具を売っていたのに、図書館でしか遭遇しないような「テナシティー(頑健さ)」とか「ユービキタス(偏在する)」といった聞きなれない単語を日常会話のなかにちりばめていました。
会話の感じも堅苦しく、「注文を逸することで、筆舌に尽くし難い、絶望感に襲われます。その効果が証明されている営業の原理を応用するために必死に努力しているのですが、通例、結末には礼儀正しく拒絶されてしまうのです。」のような感じです。
私やあなただったら、「必死でやっているんだけど、なかなか売れないんだ。ほんと、がっかりだよ。」と言うところでしょう。
私はポールにウェブと話したいのでちょっと部屋を借りたいと伝え、その部屋に二人で入りドアを閉めました。
「ウェブ、今から良いことアドバイスしようと思うが、聞いてくれるか。それとも、もっと自分の性格に合った仕事を探してみるかい。」
「もし、そうお考えになることが、ご自身のお力で…」と言ったところで遮って、
「聞いてくれ、ウェブ。君はいい奴だし、見かけといい頭の良さといい、素養はすばらしい。ポールも言っていたが、商品知識も豊富だ。
「でも、君に困ったところがあることにも気が付いたよ。僕は、君からはコーヒー・テーブルを買わないよ。なぜか、教えてあげよう。君が言葉使いは、僕を遠ざけるんだ。君の立ち振る舞いや言葉使いの品格は、僕よりはるかに上をいっていて、君のことを自分と同じ目線にいる、同じような人間として見ることができなくなるんだ。」
「言い方を変えると、君はカルチェで宝飾品を売っているわけでもないし、パーク・アヴェニューでロールスロイスを売っているわけじゃない。君は平均的収入の人々に普通の商品を売っている家具のセールスマンだよ。」
「君は、えせインテリではない。ただ、そういう印象を与えてしまっている。君が休みの日に何をしているのかは知らない。でも、たぶんオペラのシーズンチケットを取ったり、シェークスピアを読んだりしているんじゃないかと想像してしまうのさ。理想の休暇は、バードウォッチングや美術館めぐりだとか。」
「それは良いことだよ。でも、仕事中はプロスペクトの目線まで降りて来なきゃだめだ。造語になるが、二つのハットをかぶれってことだよ。君の趣味や嗜好は休みの時だけにして、仕事中はごく普通のどこにでもいる奴のハットをかぶれ。」
「クロージングに失敗しそうな流れの中で、そのハットをかぶれ。セールス地固めの段階では、たいして意味はないことだ。なぜかというと、プロスペクトはまだ自分を守るための売り込みに対する抵抗を示しているからだ。でも、君がその抵抗をはぎ取ってしまったら、その客は、唯一最後の武器、つまりノーという言葉を使うために、あら捜しを始めるのさ。」
「君は、プロスペクトに絶好の口実を与えてしまっている。『こいつは、まったく気取ったやつだ。』とか『ウェブは自分を何様だと思っているんだろう。難しいな言葉ばかり使いやがって。よし、見返してやろう』とかだよ。
「ウェブ、試してくれ。プロスペクトに、君は自分と同格の人間だと感じさせたとき、つまり労働者として生活している人間として君を相手に同化させたとき、クロージングの勝率があがるかどうか、試してみてくれ。
数週間後、彼から手紙が届きました。「親愛なるレス、僕は今、営業のトップを走っています。二種類のハットを持つ男として仕事を楽しんでいます。プロスペクトに自分を同化させることを学んでからは、売ることがものすごく楽になりました。」との内容でした。
<マイクから一言>
営業マンは、立場もバックグラウンドもプロスペクトとは違うのですが、それでもプロスペクトに自分と同じように血の通ったひとりの人間なのだということを認知してもらわねばなりません。ウェブの場合、お高くとまっていて下界まで下りて来ない雰囲気のせいで、プロスペクトに違和感を与えていましたが、逆に卑屈になりすぎてもいけません。大げさに客をおだてたり、常に下から目線に徹していることをアピールし、ちょっとでも好印象を得ようとする卑屈な態度では手記の中で言われているプロスペクトとの同化はかないません。そのような態度を全面に出していると、ここぞというときに、営業マンとして期待以上のサービスや気配りをしても、そのギャップ効果が薄れます。(1-4のマイクの一言を参照のこと)確かにトップ営業マンたちは、ここまでやってくれるのかと客が思うような段取りやサービスを提供することがあります。彼らは、失礼にもならず、横柄にもならず、お高くとまらず、卑屈にもならずに、プライドを保ちながらプロスペクトとコミュニケーションをはかり、プロスペクトと同化しながら、ギャップ効果を生みだしているのです。